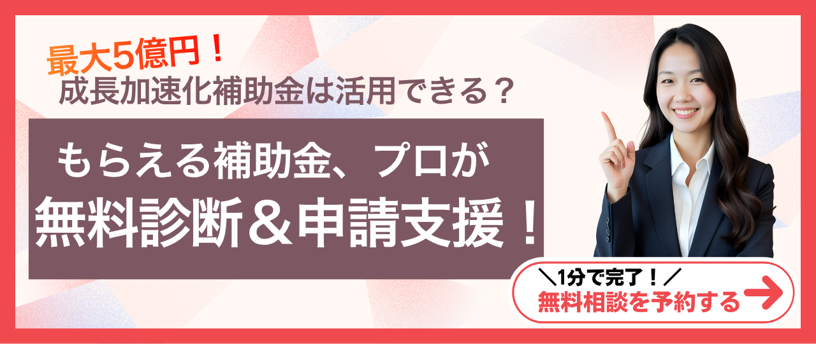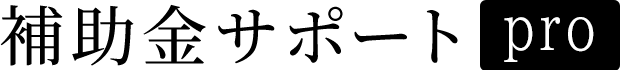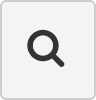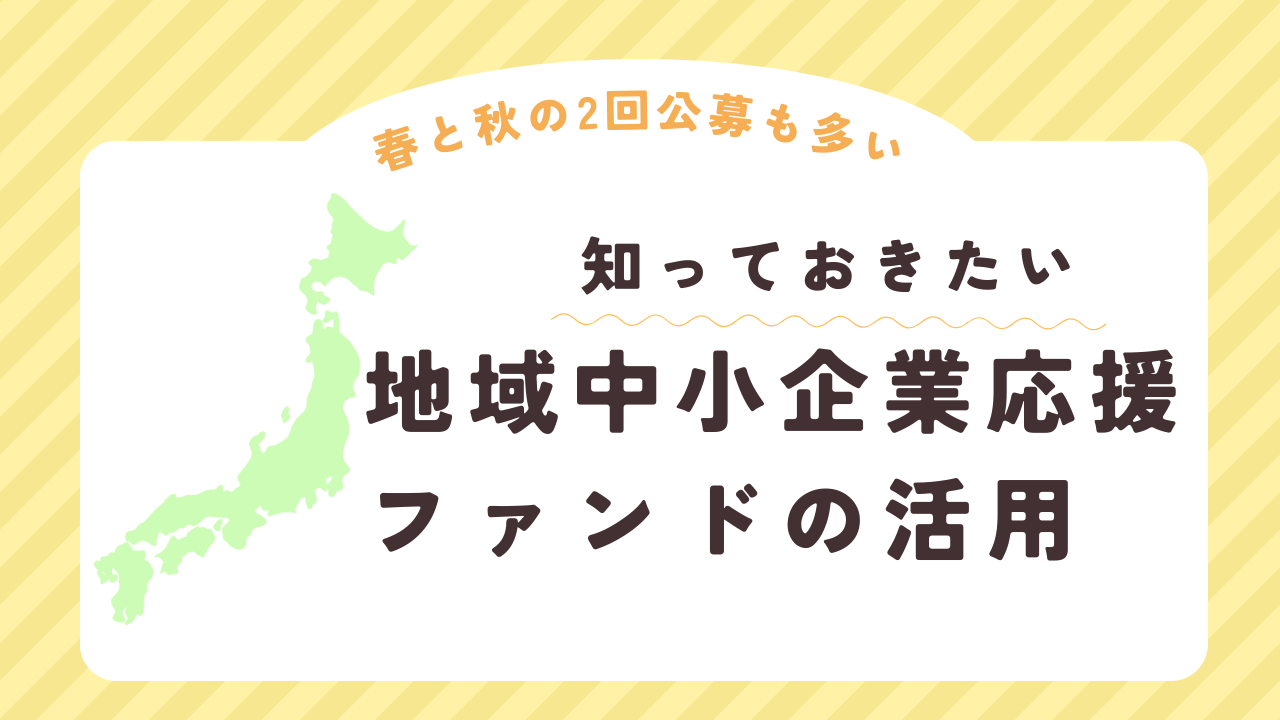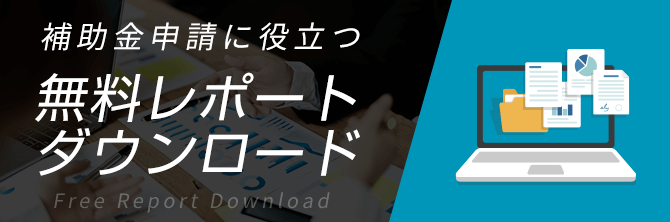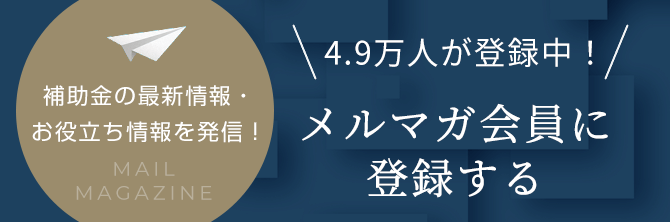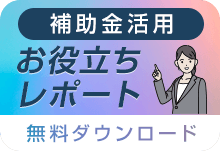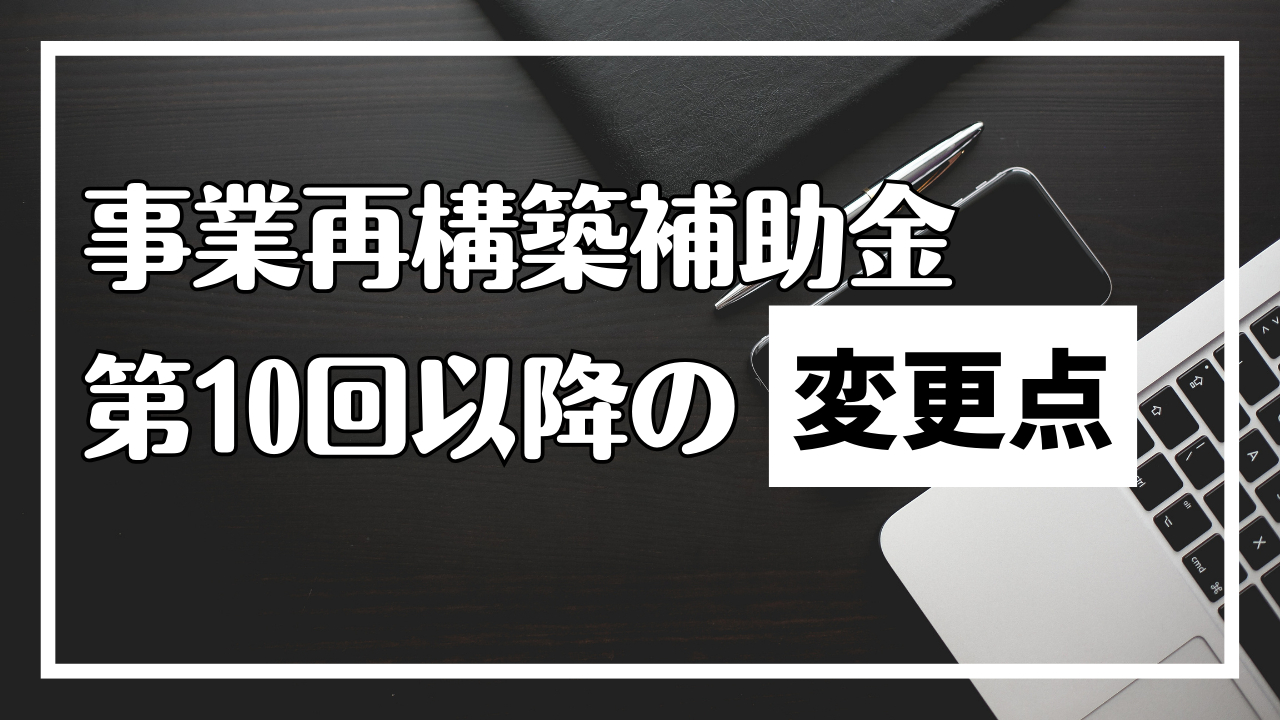
成長加速化補助金で「みなし大企業」は対象外?判定する基準
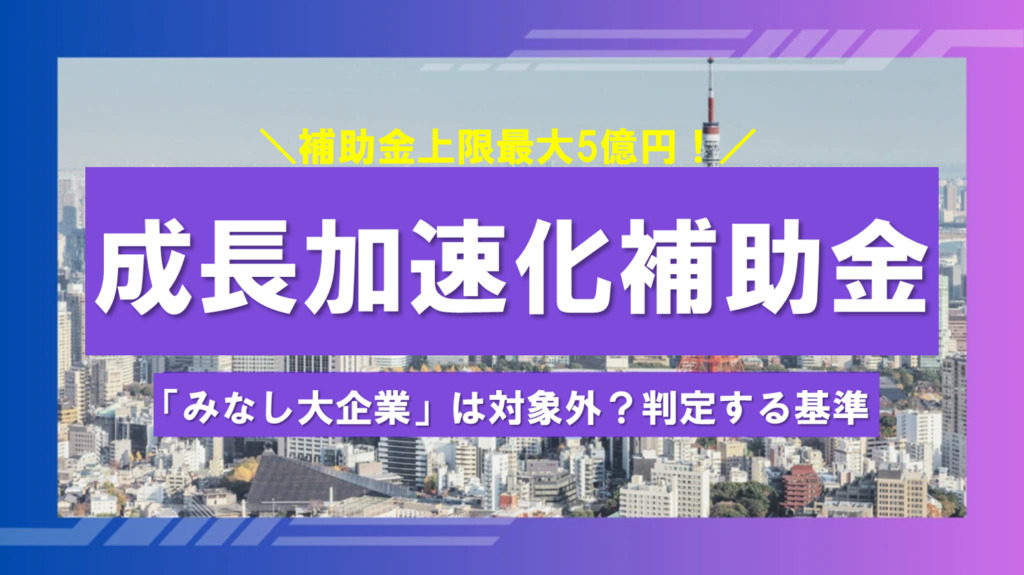
補助上限5億円という「中小企業成長加速化補助金」は、成長を目指す企業にとって大きなチャンスです。
しかし、成長加速化補助金には、みなし大企業という重要な確認事項が存在します。
成長加速化補助金みなし大企業について正しく理解しないと、申請が不採択になるだけでなく、受給後に補助金の返還を命じられるなど、深刻な経営リスクを招く可能性があります。
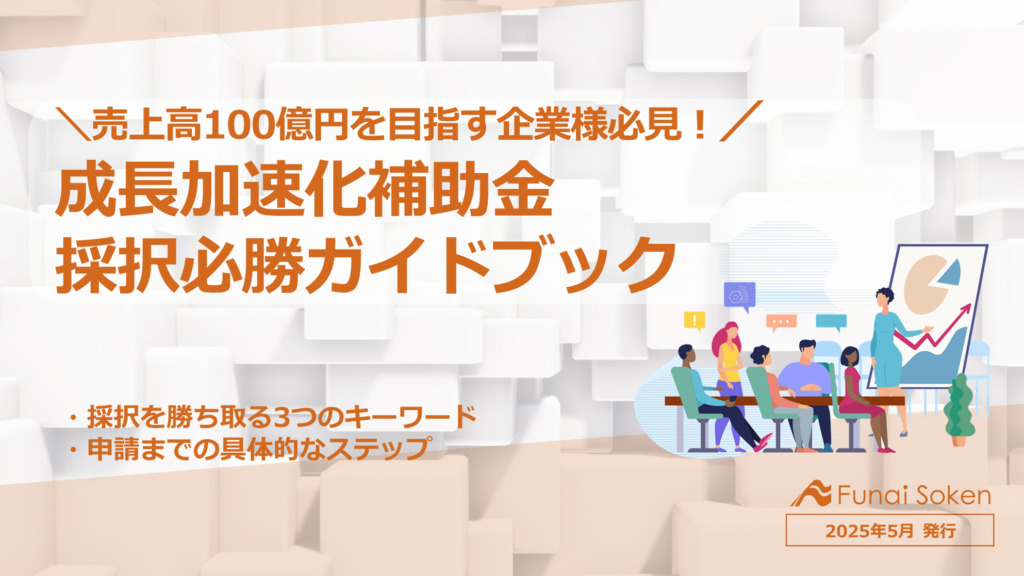
「みなし大企業」とは?定義と判断基準をわかりやすく解説
みなし大企業とは、資本金や従業員数では中小企業の基準を満たしていても、実質的に大企業の支配下にあると判断される企業のことです。
潤沢な経営資源を持つ大企業の傘下にある企業にまで中小企業向けの支援が及ぶのは不公平であるという観点から、多くの補助金で対象外とされています。
成長加速化補助金では、以下のいずれか一つでも該当すれば「みなし大企業」と判定されます 。
- 単独の大企業が、発行済株式または出資総額の1/2以上を所有している。
- 複数の大企業が、合計で発行済株式または出資総額の2/3以上を所有している。
- 大企業の役員・職員を兼ねる者が、役員総数の1/2以上を占めている。
- 上記1から3の条件に当てはまる「みなし大企業」に、株式の全てを所有されている(孫会社など)。
- 上記1から3の条件に当てはまる「みなし大企業」の役員または職員を兼ねている者が、役員総数のすべてを占めている。
この判定は、資本関係だけでなく人的な支配関係にも着目した厳格なものです。
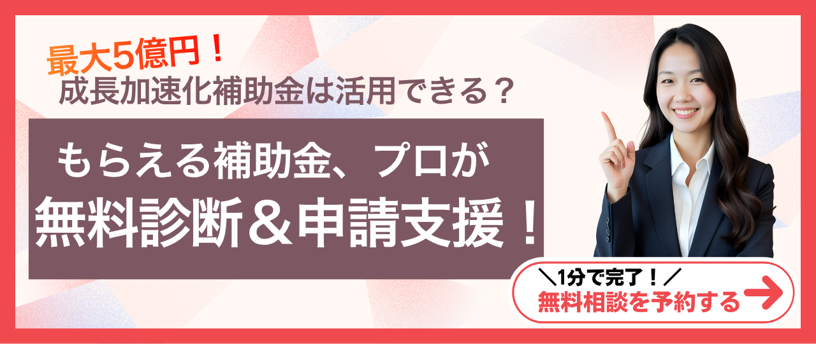
確認方法と判定ミスの重大リスク
自社が「みなし大企業」に該当しないかの確認責任は、申請者自身にあります。
ここでは、判定ミスを防ぐための具体的な調査手順と注意すべきポイントを解説します。
自社の企業規模の確認
まず、自社の資本金と「常時使用する従業員数」が、業種別の中小企業の定義の範囲内にあることを確認します 。
株主名簿の精査
最新の株主名簿を用意し、株主構成を詳細に確認します。特に、株主が法人の場合は、その法人名と出資比率を正確にリストアップします 。
法人株主の規模判定
リストアップしたすべての法人株主について、それぞれが「大企業」に該当するかを判定します。この調査方法の詳細は次項で解説します。
資本関係の上流調査
法人株主が中小企業であった場合でも、安心はできません。その中小企業のさらに親会社に大企業がいないか、資本関係を遡って調査する必要があります 。大企業が子会社(中小企業)を通じて孫会社である自社を間接的に支配しているケース(いわゆる「孫会社」スキーム)を見逃さないためです 。
役員構成の確認
役員名簿(役員一覧)を確認し、各役員の兼任状況を調べます 。他の法人の役員や職員を兼任している役員がいる場合、その兼任先の法人が「大企業」に該当しないかをStep 3と同様に調査します。
この5つのステップをすべてクリアして初めて、「みなし大企業」に該当しないと結論づけることができます。
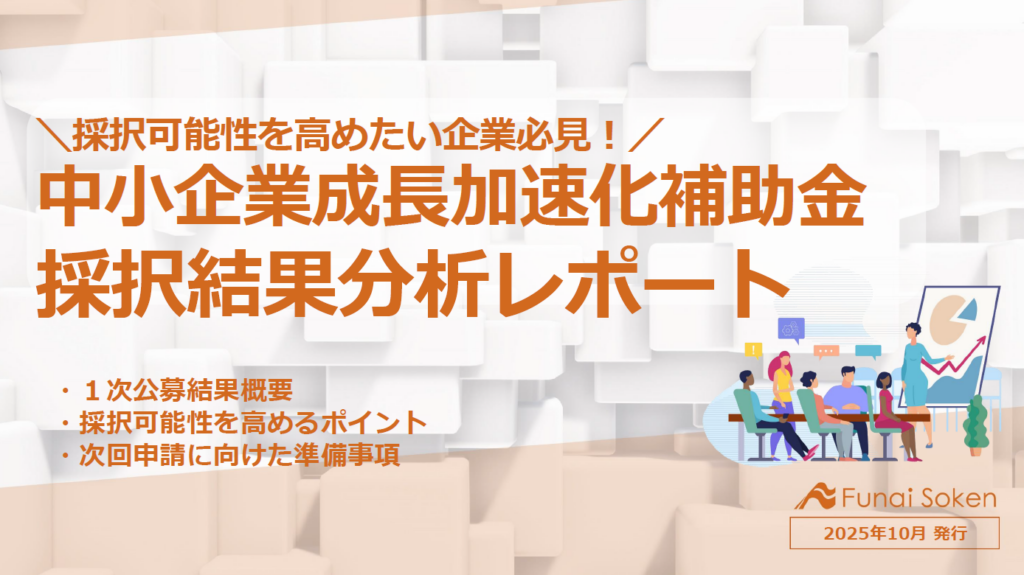
みなし大企業の判断のための調査
株主名簿や役員名簿を精査し、出資元や役員兼務先が「大企業」に該当しないかを徹底調査する必要があります。場合によっては親会社のさらに上位まで遡る調査も求められます。
特に非上場企業は従業員数など規模の把握が難しいです。ですから、正確な情報収集が自己判定の最大の課題となります。そのため、公的データベースや信用調査会社などを活用した入念な調査が不可欠です。
無料で利用できる公的情報
企業の公式ウェブサイト:
まずは相手企業の公式サイトにある「会社概要」ページを確認します。資本金や従業員数が記載されている場合があります 。
上場企業の場合
金融庁の電子開示システム「EDINET」で公開されている有価証券報告書。これが信憑性が最も高いです。資本金、従業員数、大株主構成など、詳細かつ正確な情報が記載されています 。
非上場企業の場合
登記事項証明書(登記簿謄本):
法務局で取得できます。これにより、少なくとも公式な資本金の額は確定できます。
信用調査会社のデータベース:
従業員数など、公開されていない情報を得るための最も確実な方法です。帝国データバンク(TDB)や東京商工リサーチ(TSR)などが提供する有料サービスを利用することで、信頼性の高い情報を得られます。
非上場の株主については情報収集に手間がかかる場合があります。しかし、このデューデリジェンス(適正評価手続き)を怠ると、後のリスクが非常に大きくなるため、徹底した調査が求められます。
万が一、判定を誤って補助金を受給した場合、補助金等適正化法に基づき厳しいペナルティが科されます。
出資比率・親会社構成で該当するケースと注意点
理論的な定義を理解できたでしょうか。次に、具体的な企業構造において、どのように「みなし大企業」と判定されるのかを見ていきましょう。
ここでは、よくある資本構成のパターンで「みなし大企業」に該当する、あるいはしないケースを解説します。
単純な親子上場のケース
構造: 大企業A社が、中小企業B社の株式を60%保有。
判定: B社は、発行済株式の1/2以上を単一の大企業に所有されています。そのため、「みなし大企業」に該当します 。これは最も典型的で分かりやすいパターンです。
「孫会社」のケース
構造: 大企業A社が、中小企業B社の株式を100%保有。さらに、そのB社が中小企業C社(申請者)の株式を100%保有。
判定: まず、B社がA社の子会社であるため「みなし大企業」となります。申請者であるC社は、その「みなし大企業」であるB社に100%所有されているため、C社もまた「みなし大企業」と判定され、補助金の対象外となります 。資本関係は一段階上だけでなく、そのさらに上まで遡って確認する必要があります。
複数の大企業による出資のケース
構造: 大企業A社が40%、大企業B社が30%の株式を中小企業C社(申請者)に対してそれぞれ保有。
判定: A社、B社ともに単独では1/2に達していません。しかし、複数の大企業による出資比率の合計が40% + 30% = 70%です。2/3(約66.7%)の基準を超えています。したがって、C社は「みなし大企業」に該当します。
持株会社(ホールディングス)のケース
構造:
大企業A社が、持株会社B社(中小企業)の株式を100%保有。その持株会社B社が、事業会社C社(申請者)の株式を70%保有。
判定:
ケース2と同様の考え方です。まず持株会社B社が「みなし大企業」と判定されます。申請者C社は、その「みなし大企業」であるB社に1/2以上所有されています。なので、C社も「みなし大企業」となります 。
みなし大企業に該当しない、重要ケース
構造:
親会社A社(従業員200名の中小企業)が、子会社B社(申請者、従業員350名の中小企業)の株式を70%保有。
判定:
B社はA社に過半数の株式を所有されています。しかし、その親会社であるA社自体が「大企業」の定義に該当しません。したがって、B社は「みなし大企業」には該当せず、補助金の申請資格があります 。支配関係の有無だけでなく、支配する側が「大企業」であるかどうかが決定的に重要です。
注意点は、判定のタイミングです。極めて重要なルールです。補助対象者であるかどうかの判定は、公募への申請時点で行われます。
「現在はみなし大企業だが、交付決定までには資本構成を変更して要件を満たす予定だ」
といった主張は一切認められません 。
申請書を提出するその日に「みなし大企業」に該当していれば、その申請は無効です。この厳格なルールは、補助金申請のためだけに一時的に資本構成を操作するような行為を防ぐためのものです。
もし、資本構成の変更を検討している場合は、補助金の公募開始前にすべての手続きを完了させておく必要があります。
みなし大企業でも申請できる可能性はあるのか
「みなし大企業」と判定された企業が、単独でこの補助金を申請することはできません 。
唯一の可能性。それは、補助対象となる中小企業を主体とする「コンソーシアム(共同申請)」に連携事業者として参加することです 。
この場合、事業の重要なパートナーにはなれます。しかし、補助金自体を受け取ることはできません 。
長期的な視点では、MBO(経営陣による買収)などを通じて大企業との資本関係を解消し、「みなし大企業」から脱却することも根本的な解決策となり得ます 。
まとめ
「みなし大企業」の判定は複雑で、そのミスがもたらすリスクは甚大です。少しでも判断に迷う場合は、自己判断で申請することはやめましょう。補助金専門コンサルタントや行政書士などに相談し、確実な申請準備を進めることが賢明です 。