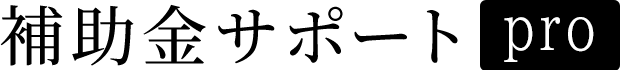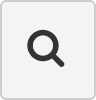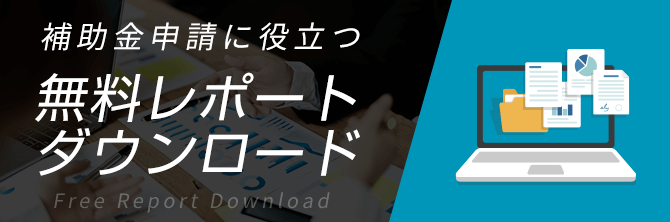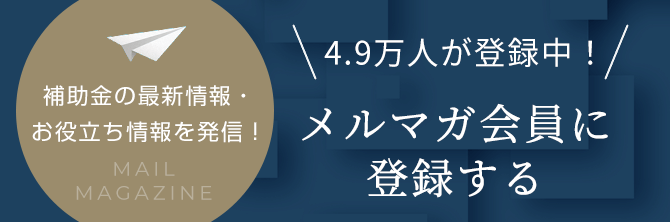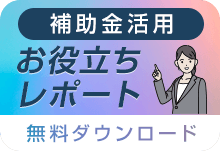補助金で“あと一歩”を埋める!パートナーシップ構築宣言のすすめ
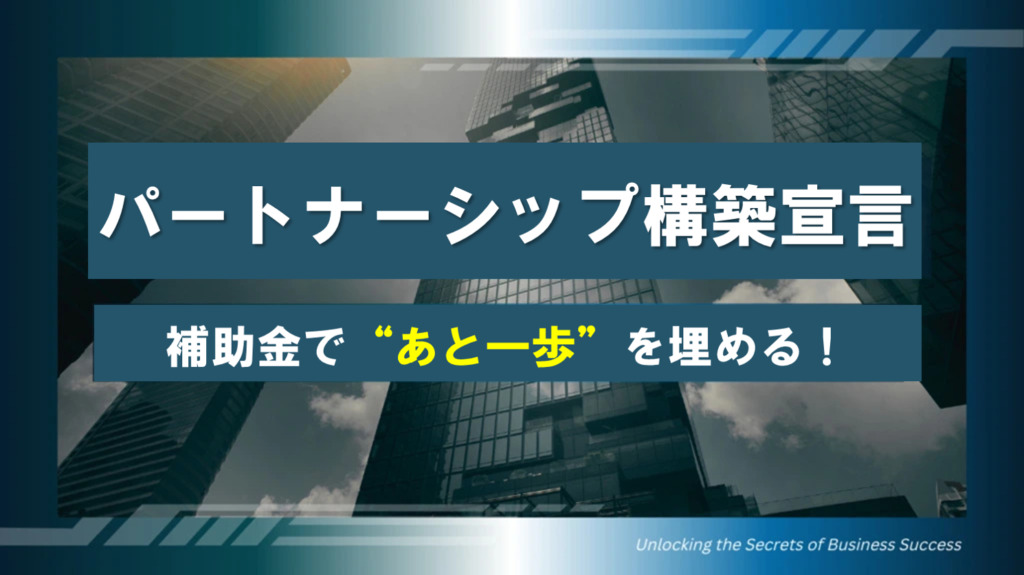
成長投資や共創に向けた補助金活用が注目される理由
近年、中小企業の成長投資を促進する政策が加速しています。
その背景には、人手不足や物価高といった経営課題、地域経済の担い手不足といった社会的要請があります。国はこうした課題に対応する手段として、補助金制度の整備を進めており、単なる経費補填ではなく「成長」「共創」「賃上げ」といったテーマを重視する傾向が顕著です。
特に、補助金の採択においては、企業単独ではなくサプライチェーン全体での取り組みや、取引先との共創に積極的な企業が優遇されるケースが増えています。
これにより、協力会社との関係性を見直し、長期的視点での戦略を再構築する企業にとって、補助金は有効な成長ツールとなっています。
パートナーシップ構築宣言とは?補助金との関係を解説
パートナーシップ構築宣言は、中小企業庁などが推進する制度で、事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で宣言するものです。
企業が取引先と共存共栄の関係を築き、適正な取引慣行や下請け配慮を明文化して宣言します。
大企業だけでなく中小企業も対象で、宣言内容は公式サイトに掲載され、企業の信頼性を高める手段としても機能します。
この宣言は、近年多くの補助金制度で加点要素として明記されており、採択可能性を高める要素としても、重要なポイントとなっています。
補助金申請に効く!パートナーシップ構築宣言が要件の制度一覧
パートナーシップ構築宣言が加点対象、あるいは申請要件となっている補助金制度はいくつか存在します。
代表的なものが「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(いわゆるものづくり補助金)です。加点要素として評価される仕組みになっています。
他に、代表的な補助事業でいうと、
・大規模成長投資補助金
・成長加速化補助金
・新事業進出補助金
・事業再構築補助金
などもパートナーシップ構築宣言の公表有無を確認する項目があり、加点等の対象となっています。
さらに、近年は地方自治体が独自に行う補助金でも、宣言取得が前提となるケースが増加傾向にあり、今後は「要件化」も進むと見られます。
補助金を継続的に活用したい企業にとっては、早期に宣言を取得しておくことが賢明な戦略と言えるでしょう。
パートナーシップ構築宣言から補助金申請までの流れ
1.活用したい補助金の選定と要件確認
- 「新事業進出補助金」や「ものづくり補助金」など、加点対象となる制度を調査
- 宣言の有無が加点要素になっているか確認
2.パートナーシップ構築宣言の内容検討
- 自社の取引方針、共創姿勢、適正取引の方針などを整理
- 公表される内容のため、経営方針との整合性も重視
雛形をパートナーシップ構築宣言サイトよりダウンロードすることが可能です
3.パートナーシップ構築宣言の登録・提出
- 専用ウェブサイトから申請(中小企業も可能)
- 審査後、ポータルサイトで企業名と宣言内容が公開
- 通常、1週間程度で公開される
4.補助金申請に必要な事業計画書等の作成
- 事業の目的、投資内容、スケジュール、財務計画を詳細に記載
- 宣言取得済みである旨を申請画面内で選択、もしくは申請資料に明記する
- 必要に応じて外部専門家に依頼して事業計画書の精度を高める
5.補助金申請の実施と採択結果の待機
- 公募期間内にオンライン申請
- 採択結果が出るまでに1〜2ヶ月程度かかるのが一般的
この流れを理解しておくことで、補助金申請の準備がスムーズになり、採択率向上にもつながります。
まとめ:パートナーシップ構築宣言で補助金採択の可能性を広げよう
パートナーシップ構築宣言は、補助金申請のための「加点対策」としてだけでなく、企業の社会的姿勢や取引姿勢を示す有効な手段です。
協力会社との信頼関係の再構築や、賃上げを含めた働き方の改善、共創を前提とした新事業開発など、現代の経営に求められるテーマと強く結びついています。
今後、補助金制度の要件や審査基準がさらに厳格化される可能性を考えると、「パートナーシップ構築宣言を取得していない企業」との差が広がるかもしれません。
今のうちに体制を整え、成長資金として補助金を活用する準備を進めておき、パートナーシップ構築宣言を公表することで、競争力ある企業運営につながります。
補助金活用を真剣に考えるなら、宣言取得は“必須の第一歩”です。